テレワークでも“つながる職場”を実現!社内コミュニケーション改善の実践ガイド
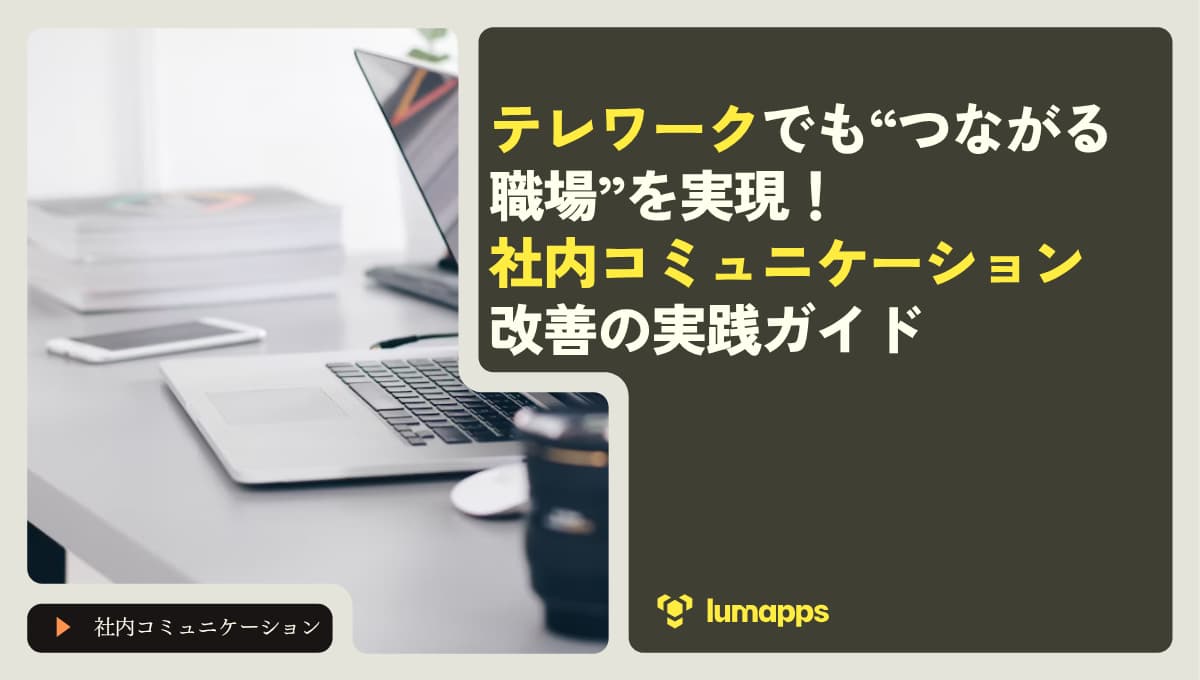
目次
テレワークの普及により、働き方の自由度は飛躍的に高まりましたが、その一方で「社員同士のつながりが感じられない」「雑談や相談が減って孤独を感じる」といった声も多く聞かれるようになりました。組織の生産性やエンゲージメントを維持するためには、リモート環境に適した社内コミュニケーションの仕組みづくりが不可欠です。
本記事では、テレワークにおけるコミュニケーション課題の本質を明らかにしながら、今日から実践できる改善策とツールの活用法、さらに大手企業・中小企業それぞれの成功事例までを詳しく解説します。つながりを実感できる職場環境の構築を目指す企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
社内コミュニケーションを阻むテレワーク時代の課題とは
テレワークの導入により、時間や場所にとらわれない働き方が実現した一方で、社員同士のつながりや意思疎通の面では新たな壁も生まれました。特に、日々の業務におけるちょっとしたやりとりや、職場での空気感の共有といった“人と人との距離”にまつわる部分で、多くの企業が課題を感じ始めています。
ここでは、テレワーク環境において顕在化しやすいコミュニケーションの問題点を具体的に見ていきましょう。
テレワークで起こりやすいコミュニケーションギャップ
テレワークの普及により、業務上の必要最低限のやりとりは維持できていても、対面での勤務に比べて“ちょっとした雑談”や“ふとした声かけ”といった非公式なコミュニケーションの機会が極端に減少しました。こうした非言語的・感情的なつながりは、職場の信頼関係を築くうえで欠かせない要素です。
たとえば、オフィスであれば「この件、どうなった?」とその場で聞けたことも、テレワークではわざわざチャットやメールを送る必要があり、心理的ハードルが上がります。その結果、小さな情報共有がされにくくなり、認識のズレや誤解を招くケースが増加します。また、表情や声のトーンといった非言語情報が伝わりにくいため、意図が正確に伝わらず、摩擦が生じることもあります。
特に注意すべきなのは、業務に直接関係のない“余白のコミュニケーション”が失われがちである点です。プロジェクト外での雑談や日常会話は、チームメンバーの人となりを知り、心理的な安全性を醸成するうえで非常に重要です。これらがなくなることで、社員同士の関係性は希薄になり、チーム全体の一体感が損なわれるリスクが高まります。
社員の孤立感やエンゲージメント低下
リモートワーク環境では、自分が周囲からどう見られているのかがわかりづらく、評価されている実感や会社への貢献度が見えにくくなります。このような不透明さは、特に若手社員や中途入社者にとっては大きな不安要素となります。
さらに、ちょっとした悩みや不安を気軽に相談できる相手が近くにいないため、心の中にストレスを溜め込んでしまうことも少なくありません。たとえば、困っていることがあっても「こんなことで聞いていいのか」とためらい、誰にも相談できないまま問題が深刻化することもあります。
こうした状況が続くと、社員は次第に組織からの疎外感を感じるようになり、エンゲージメントが低下します。結果として、仕事への意欲が薄れ、生産性の低下や離職リスクの増加につながります。特にオンボーディング期にある社員に対しては、意図的に接点を設け、帰属意識を高める取り組みが求められます。
オンライン疲れ・ツールの乱立によるストレス
テレワークでは、生産性向上を目的に多くのコミュニケーションツールが導入されがちですが、結果として「ツール疲れ」に陥るケースも増えています。チャットツール、社内SNS、ビデオ会議、タスク管理ツールなどが乱立することで、どのツールで何を共有すべきかが曖昧になり、社員は常に情報に追われる状態になります。
特にビデオ会議は、対面会話に比べて集中力を要するため、長時間の参加は著しい精神的疲労を引き起こします。これに加えて、表情の確認や相づちのタイミングなどに気を配る必要があり、常に「画面越しの対話」に気を張り続けなければなりません。こうした「Zoom疲れ」は、日々の業務への集中力を奪い、パフォーマンス低下の一因になります。
また、ツール間の通知が重複することや、メッセージの確認漏れが起こることで、ストレスが蓄積し、仕事そのものへのモチベーション低下を招く恐れもあります。ツールは便利な反面、使い方を誤ると業務効率どころか社員のメンタルヘルスにも影響を及ぼすため、慎重な選定と運用ルールの整備が不可欠です。
関連記事:ハイブリッドワークとは?導入メリット・成功事例・課題を徹底解説
テレワークでも強いチームを作る!コミュニケーション改善のポイント
オフィスに集まらずに働くスタイルが当たり前になった今、企業に求められているのは「距離があっても信頼できる関係」をどう築くかという視点です。物理的に離れていても、社員が互いに安心して意見を出し合い、チームとして成果を出すためには、従来とは異なる形のコミュニケーション設計が欠かせません。
ここでは、テレワーク下でも強いチームを維持・育成するために有効な、具体的なコミュニケーション改善のポイントを紹介します。
定期的な1on1と雑談機会の仕組み化
上司と部下が1対1で向き合う1on1ミーティングは、テレワーク下で最も効果的なコミュニケーション手段の一つです。業務の進捗確認だけでなく、悩みや不安を共有する場にもなり、心理的なケアにもつながります。
また、意図的に「業務外の雑談」を行う機会を作ることで、カジュアルな会話が生まれやすくなり、メンバー間の信頼関係も深まります。たとえば、週に一度の“ランチ雑談”や“バーチャルコーヒーブレイク”などの施策は、日常的なつながりを維持するうえで有効です。
朝会・夕会のオンライン化
チームとしての一体感を維持するには、定期的な集まりの時間を設けることも重要です。毎朝の朝会や業務終了前の夕会をオンラインで実施することで、日々の進捗共有や軽い雑談がしやすくなります。
こうしたミーティングでは、単なる業務報告にとどまらず、チームの雰囲気づくりや、他メンバーの状況把握にもつながります。実際にサイバーエージェントでは、朝会・夕会をオンライン化したことで、部署を超えた情報共有とチーム連携が強化されています。
チャットツールの活用とルール整備
チャットツールは、テレワークにおいて欠かせないコミュニケーションインフラです。SlackやMicrosoft Teamsといったツールは、即時性と柔軟性を持ちながら、非同期のやりとりを可能にする利点があります。
しかし、通知の多さや連絡の重複、情報の埋もれといった課題も見逃せません。そのため、チャンネルごとの目的を明確にし、業務用と雑談用のスペースを分けておくなど、ルールを設けたうえで活用することが推奨されます。あわせて、定期的に利用状況を見直す運用改善も重要です。
バーチャルオフィスの導入効果
リアルな職場の空気感を再現する手段として、バーチャルオフィスの活用も注目されています。oViceやSpatialChatなどのツールを使えば、画面越しであっても「偶然の立ち話」や「隣の席の声かけ」といったオフィスならではのコミュニケーションを再現できます。
常時ログイン状態を前提にすることで、社員同士が気軽に声をかけ合える環境が生まれ、孤立感の軽減や連携のしやすさにも寄与します。特に、プロジェクトを横断して関わるメンバーが多い企業にとっては、有効な取り組みとなるでしょう。
社内ツールの選定と運用で変わるテレワークの質
テレワーク下での業務効率とチームのつながりを保つうえで、どのようなコミュニケーションツールを使うかは、業務の質そのものに直結します。しかし、単に便利そうなツールを導入するだけでは十分とは言えません。選定時の目的意識と、導入後の定着・運用までを見据えた仕組みが求められます。
ここでは、コミュニケーションツールの種類と選び方、そして現場で確実に活用されるための運用上の工夫について解説します。
コミュニケーション系ツールの種類と特徴
テレワークでは、従来の電話やメールに代わり、チャットツールやビデオ会議、社内SNSといった多様なツールが活用されるようになりました。それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることが生産性を高めるカギとなります。
たとえば、チャットツールは、リアルタイムのやりとりに適しており、ちょっとした確認や意思決定を迅速に進めるのに有効です。一方で、ビデオ会議ツールは、複雑な議題や感情の共有を伴う場面で活躍します。また、社内Wikiや社内SNSのような情報蓄積型のツールは、プロジェクトごとのナレッジ共有や過去ログの整理に適しており、チーム内の属人化を防ぐ効果もあります。
重要なのは、1つのツールで全てをまかなうのではなく、業務内容や社員の利用シーンに応じて複数を併用しつつ、混乱を防ぐための整理とガイドラインを用意することです。
導入時の定着支援とマネジメントのコツ
せっかく優れたツールを導入しても、社員に活用されなければ意味がありません。特に新しいシステムに対しては「慣れないから使わない」「使い方がわからない」といった理由で、現場に浸透しないケースが多く見られます。
そのため、導入初期にはトレーニングやマニュアルの提供が不可欠です。動画チュートリアルやQ&Aセッションを用意することで、社員の不安を解消しやすくなります。また、管理職が率先してツールを活用し、利用の目的やメリットを繰り返し発信することで、現場の心理的ハードルを下げる効果が期待できます。
さらに、ツールの利用ルールやマナーを社内で明文化し、誰もが安心して使える環境を整えることも大切です。たとえば、「返信の必要がないメッセージにはリアクションで済ませる」「業務連絡と雑談を分ける」といったルールを設けることで、コミュニケーションの質と効率が大きく向上します。
こうした定着支援を丁寧に行うことで、単なるツール導入ではなく、“組織文化としての活用”へと昇華させることが可能になります。

テレワーク下でも社員の声を拾うために
リモートワークでは、物理的な距離があるぶん、社員の状態や気持ちの変化を察知するのが難しくなります。だからこそ、組織として「声を拾う」仕組みを意識的に整備することが重要です。業務の成果だけでなく、社員の声に耳を傾ける姿勢が、エンゲージメント向上や離職防止にもつながります。
エンゲージメントサーベイや匿名アンケートの活用
テレワークでは、日々の表情や雑談から社員の様子を感じ取ることが難しくなります。そのため、数値で可視化できるエンゲージメントサーベイと、自由記述を含めた匿名アンケートを併用することで、社員の本音を捉えることができます。
エンゲージメントサーベイでは、業務満足度、組織への信頼感、働きやすさなどを定期的に数値で把握できるため、組織全体の状態を客観的に分析するのに役立ちます。一方で、自由記述式のアンケートでは、改善してほしい点や悩み、提案など、個々の生の声を収集することができます。
たとえば、「最近困っていることはありますか?」というシンプルな質問でも、匿名であれば本音が出やすく、施策の見直しにつながるヒントが得られることもあります。こうした仕組みを定期的に実施することで、社員の心理的安全性を保ちつつ、職場の改善を図ることが可能になります。
フィードバック文化の醸成
声を拾うだけではなく、それを活かす文化づくりも不可欠です。上層部からの一方向的な通達だけでなく、現場の意見や提案に対しても耳を傾ける姿勢を示すことが、双方向の信頼関係を生み出します。
たとえば、アンケート結果を社内で共有し、改善施策を実行に移すプロセスをオープンにすることで、社員は「自分たちの声が組織を動かしている」と実感できます。こうした積み重ねが、社員の主体性や自律性を高め、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。
また、日常の中でフィードバックを交わすことが習慣になれば、些細な問題も早期にキャッチしやすくなり、大きな課題へ発展する前に対応することが可能です。定例会議での「Good & Improvement共有」や、1on1での気軽な振り返りなど、場面ごとの工夫を取り入れることで、自然なフィードバックの文化が育っていきます。
関連記事:デジタルワークプレイスはDX時代に求められるソリューション!活用事例も解説
テレワーク×コミュニケーション改善の成功事例
制度やツールを整えても、それをどう運用するかによって成果は大きく異なります。テレワーク環境下でのコミュニケーション課題に対し、試行錯誤を重ねながら独自の工夫で乗り越えてきた企業も多く存在します。ここでは、大企業と中小企業それぞれの実践事例から、具体的な取り組みと得られた効果を紹介します。
大企業での成功例:富士通・サイボウズなど
富士通は、2020年以降、全社員を対象に原則フルリモート勤務へと移行しました。物理的な出社を前提としない働き方に対応するため、コミュニケーション基盤の整備と業務プロセスの見直しを同時に進めました。たとえば、オンライン会議は原則1時間以内、資料は事前共有といったルールを徹底し、時間と情報の効率的な活用を実現しています。
参考:ニューノーマルにおける新たな働き方「Work Life Shift」を推進 | 富士通
また、サイボウズでは「働き方の多様性」を推進し続けており、リモート勤務と出社勤務を柔軟に組み合わせる“選べる働き方”を制度化しています。そのうえで、部門ごとに雑談チャットやオンライン雑談会を設け、日常的なつながりの維持にも力を入れています。こうした取り組みは、エンゲージメント向上や離職防止にも寄与しており、社員からの満足度も高い評価を得ています。
中小企業での工夫と成果
限られた人員や予算の中でも、創意工夫によりテレワーク下でのコミュニケーション改善に成功している中小企業もあります。たとえば、社員数30名のITベンチャー企業では、毎週1回の「1on1ミーティング」を全社員と実施し、業務以外の相談にも耳を傾ける機会を設けています。これにより、早期の課題発見と信頼関係の構築が進みました。
さらに、毎月開催される「バーチャルランチ会」では、部署をまたいだメンバー同士の交流が生まれ、心理的距離の縮小にもつながっています。また、Slackでは「雑談専用チャンネル」を設け、業務外の趣味や日常の話題も気軽に共有できる場として活用されています。こうした小さな積み重ねが、組織内の風通しを良くし、実際に離職率の改善や社員満足度の向上といった具体的な成果を生み出しています。
まとめ
テレワークが常態化する今、職場のつながりを維持・強化するには、意識的なコミュニケーション設計がこれまで以上に求められます。ツールの導入や制度の整備はスタート地点にすぎず、そこから実際に機能させていくためには、社員の声に耳を傾ける姿勢と、運用面での継続的な工夫が欠かせません。
1on1の定期実施、バーチャル雑談の場づくり、エンゲージメントサーベイの活用、そしてフィードバックを受け入れる文化の醸成など、すぐに始められる施策は数多くあります。こうした積み重ねこそが、物理的な距離を超えて信頼関係を育み、“つながりを実感できる職場”を形づくるのです。
貴社でもまずは小さなアクションから、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。テレワーク時代における新しいチームづくりは、今この瞬間から始めることができます。








