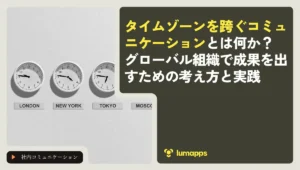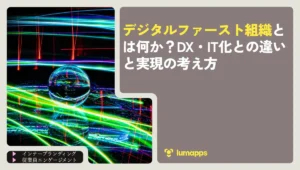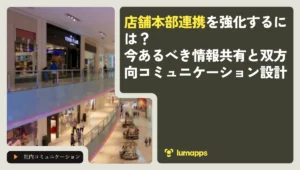組織コミュニケーションとは?重要な理由と活性化のための具体策を紹介

目次
企業における組織コミュニケーションの不足は、経営層と従業員の方向性の乖離を招き、業績の低下につながる可能性があります。一方、円滑な組織コミュニケーションを確立している企業では、従業員のエンゲージメント向上や生産性向上、組織文化の醸成を実現しています。
本記事では、組織コミュニケーションの重要性と活性化のための具体策を紹介します。持続的な成長を目指す経営者や人事担当者は、ぜひ参考にしてください。
組織コミュニケーションとは?
組織コミュニケーションとは、経営層から現場まで情報が適切に伝達され、双方向の意見交換が行われる状態を指します。組織コミュニケーションがうまく機能していると、仕事の効率が上がり生産性も向上します。
ただし、組織コミュニケーションを上手く機能させるのは簡単ではありません。経営陣と社員が気軽に話せる雰囲気づくりや、部署間の壁を取り払うような取り組みが必要です。定期的な全体ミーティングを開いたり、社内SNSを導入したりするのも方法のひとつです。
組織全体が一つのシステムとして機能するためには、情報が円滑に流通し、必要な部署や人へ適切に届くことが不可欠です。
組織コミュニケーションが重要な3つの理由
業務効率化・生産性向上
組織コミュニケーションが活発になれば、業務の効率と生産性が向上します。スムーズに情報が共有されるため、ある部署の成功事例がすぐに全社全体に共有されるからです。
社員同士のつながりが深まり、「困ったときは支え合う」文化が根付くことで、部門間の連携が強化されます。その結果、商品やサービスの品質が向上し、顧客満足度の向上につながります。さらに、顧客満足度の向上が企業の業績を押し上げる要因となります。
リモートワークや在宅勤務の普及により、対面でのコミュニケーション機会が減少しています。接触頻度が減る中でも仕事の質を落とさないためには、いかに上手くコミュニケーションを取れるかが鍵となっています。オンラインミーティングの頻度を増やしたり、チャットツールを活用したりするのも、離れていても情報共有ができるようにする具体策です。
このように業務効率や生産性を維持・向上させるには、組織コミュニケーションの取り組みが不可欠なのです。
企業理念やビジョンの把握
企業理念やビジョンを全員で共有する点も組織コミュニケーションの重要な役割です。組織コミュニケーションが機能していれば、会社がどこを目指しているのか、何を大切にしているのかを、社長から新入社員まで全員が理解し共感している状態になります。
仮に「5年後に業界トップを目指す」というビジョンが組織全体に浸透していたとします。営業部門は「もっと顧客を増やそう」、開発部門は「他社に負けない製品を作ろう」と、それぞれの立場で目標に向かって自走するようになるでしょう。
また企業理念やビジョンが把握されていれば、社員一人ひとりの仕事へのモチベーション向上にもつながります。社員個人が自ら考え行動するようになり、積極的にアイデアを出したり、新しいことにチャレンジしたりする人が増えていきます。
このように組織コミュニケーションを通じて理念やビジョンが共有されれば、会社全体の方向性が一致し、組織や個人が大きな成果を生み出すようになるのです。
柔軟で開かれた職場の構築
組織コミュニケーションが活発な組織の特徴として、誰もが気軽に意見を言えるような「風通しの良さ」があげられます。新入社員でも良いアイデアがあれば躊躇せずに提案できる、柔軟で開かれた職場が構築されているのです。
小さな誤解や不満も早めに相談できる環境なので、人間関係のトラブルは最小限に抑えられます。社員のストレスも減るため、「この会社で長く働きたい」と思う人も増え、優秀な人材の流出を防げるでしょう。
柔軟で開かれた雰囲気は、新しいアイデアを生み出す土壌にもなります。営業部門と開発部門の人が気軽に会話できるため、「こんな新商品があったらいいな」というアイデアが雑談から生まれます。部署の壁を越えた交流が増え、今までになかった化学反応が起きやすくなるのです。
組織コミュニケーションを大切にすることで、社員が生き生きと働ける環境となり、新しいアイデアや強い組織力が生まれます。長期的に見て会社の大きな強みになるはずです。
組織コミュニケーションが不足する6つのリスク
組織コミュニケーションが不足している職場では、以下の6つのリスクが見られます。
- ミスやトラブルの発生
- 離職率の増加
- コンプライアンス違反が起こりやすい
- 顧客の信用を損なう
- 職場の人間関係が悪化
- 作業品質が低下
自社に当てはまるか、ご確認ください。
ミスやトラブルの発生
組織内のコミュニケーションが不足すると、ミスやトラブルの増加が目につくようになります。営業部門と製造部門のコミュニケーションが不足していると、顧客に約束した納期が正しく伝わらず納品の遅延を起こしてしまうでしょう。
些細な疑問が放置されてしまうのもコミュニケーション不足が原因です。「ちょっと聞きづらいな」と思って確認しないまま作業を進めてしまった結果、後になって大きなトラブルに発展してしまうこともあり得ます。
大切なのは、小さなミスや疑問をそのままにしないことです。定期的なミーティングで進捗確認したり、チャットツールで気軽に質問できる雰囲気を作ったりすれば、早めに問題を発見し対処可能です。
ミスやトラブルを完全になくすことはできません。大事なのはミスやトラブルをいかに早く発見し、適切に対処することです。組織コミュニケーションを機能させて、小さな問題が大きな危機に発展するのを防ぎましょう。
離職率の増加
組織コミュニケーションの機能不全は、社員の離職率にも影響します。上司からの指示が曖昧で何をすればいいのかわからないという職場では、社員のモチベーションは低下してしまうでしょう。
コミュニケーション不足によって、常にストレスフルな職場も存在します。同僚との関係がぎくしゃくしている職場では、毎日の通勤が苦痛になってしまいます。自分の意見や提案が全く聞き入れられなければ、やる気を失ってしまうでしょう。
最近ではリモートワークが増えているため、対面でのコミュニケーションが減っています。これまで以上に、意識的にコミュニケーションを取らなければ疎遠になってしまいます。
人は「自分が大切にされている」と感じられない職場では働く意欲を失います。組織コミュニケーションを大切にすれば、社員一人ひとりが「この会社で頑張りたい」と思えるようになるでしょう。結果的に離職率の低下につながり、長期的には会社の成長にもつながります。
コンプライアンス違反が起こりやすい
コンプライアンス違反は、組織コミュニケーション不足によって起きる場合があります。新しい法律や規制の情報が現場まで伝わっていなければ、知らないうちに担当者がコンプライアンス違反を起こしてしまうこともあるでしょう。
コミュニケーション不足の状態では、互いの仕事に対して無関心になってしまいます。「隣の部署で何をしているか知らない」「他人の仕事には口出ししない」という雰囲気が広がり、不正行為を見逃してしまう可能性が高くなります。
プレッシャーや孤立感から、「誰も見ていないから大丈夫」「こんなことをしても誰も気づかないだろう」という考えが生まれ、不正行為が行われる場合もあるのです。
コンプライアンス違反を防ぐには、単にルールを設けるだけでは不十分です。社員全員が「なぜそのルールが必要なのか」を理解し、注意し合える環境を作らなければなりません。コミュニケーションを活発にして、問題を早期に発見・対処できる組織を作りましょう。
顧客の信用を損なう
組織内のコミュニケーション不足は、顧客の信用を失うリスクをもたらします。
情報が共有されていない状況では、顧客からの問い合わせに異なる回答をしてしまい相手を混乱させてしまいかねません。「Aさんに聞いたら○○と言われたのに、Bさんに聞いたら××と言われた」といった状況は、顧客の不信感を招きます。
また、社内のモチベーション低下は、直接顧客サービスの質の低下につながります。従業員が会社の方針や目標を理解していなければ、顧客対応が消極的になったり、要望に柔軟に対応できなかったりといった状況が生じ、顧客満足度を低下させてしまうのです。
顧客の信頼を獲得・維持するためには、組織全体が一丸となった取り組みが必要です。定期的な部門間ミーティングを開催して情報共有を徹底したり、顧客フィードバックを全社で共有し、改善策を議論したりするのも良いでしょう。従業員が生き生きと働ける環境を作り、顧客の信頼を獲得してください。
職場の人間関係が悪化
人間関係が悪化している職場は、組織コミュニケーションの不足が考えられます。互いの状況を知らないために、「あの人は仕事をサボっている」「この部署は自分たちの都合ばかり考えている」といった誤解や偏見が生まれる場合もあるのです。
メールの言葉遣いを冷たく感じてしまい、「あの人は私のことを嫌っているんじゃないか」と思い込んでしまう人もいるでしょう。会議での発言を誤解して、「あの部署は私たちの提案を潰そうとしている」と勘ぐってしまう人もいるかもしれません。いずれも組織コミュニケーションが機能していれば、見られない状況です。
職場の人間関係を良好にするには、意識的にコミュニケーションの機会を増やすことが大切です。部署を超えたプロジェクトチームを作ったり、ランチタイムに異なる部署の人と食事をする「シャッフルランチ」を導入したりするのも良いでしょう。
組織コミュニケーションを活性化させ、「一緒に働く仲間」という意識を育んでください。
作業品質が低下
組織コミュニケーション不足は、作業品質の低下も引き起こします。
プロジェクトの目的や重要性が共有されていなければ、社員が「なぜこの仕事をしているのか」を理解できず、低いモチベーションで仕事を行う場面もあるでしょう。また、部署間の連携が不十分であれば、重複作業や無駄な作業が発生します。これは時間の無駄であり、結果的に全体の作業効率を下げてしまいます。
コミュニケーションが不足すれば、ノウハウや成功事例の共有は困難です。「自分の部署ではこうやっているけど、他の部署ではどうしているんだろう?」という疑問が解消されないまま、非効率な作業方法が続いてしまいます。品質向上のためのフィードバックですら、コミュニケーション不足によって滞ってしまいます。
高品質な仕事は、組織全体の協力があって初めて実現します。組織コミュニケーションを機能させ、一人ひとりの知恵と経験を結集し、より良い製品やサービスを生み出しましょう。

組織コミュニケーションを活性化させる具体策
組織コミュニケーションを活性化させる具体策は下記の5つです。
- 1on1ミーティング
- 社内報
- コミュニケーションツールの導入
- シャッフルランチ
- フリーアドレス制度
順番に詳しく解説します。
1on1ミーティング
1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に行う個別面談で、組織コミュニケーションを活性化させる効果的な方法です。通常15〜30分程度で、週1回から月1回のペースで実施されます。
1on1ミーティングの目的は、単なる業務報告ではなく、部下の成長を支援し信頼関係を構築することです。効果的な1on1ミーティングを行うためには、「最近の成果」「直面している課題」「今後の目標」などのテーマを設定し、部下に事前に考えてもらうと良いでしょう。
上司は、「あなたならどうする?」といった質問を投げかけ、部下自身に考えさせることが大切です。ミーティングの最後には必ず具体的なアクションプランを決めることで、次回までの成長につなげることができます。
社内報
社内報は、単なる情報共有ツールではありません。組織文化の醸成と従業員エンゲージメント向上につながるからです。
社内報を効果的に使用するには、経営陣からのメッセージを含め、会社のビジョンや戦略を明確に示しましょう。各部署の活動紹介も行えば、普段接点の少ない部門の仕事内容を知る機会となり、部門間の連携促進にもつながります。
個人の成功事例や貢献を紹介するのもおすすめです。「今月の頑張った社員」といったコーナーを設ければ、社員のモチベーション向上に役立ちます。また、社内報の制作過程自体を、部門横断的なプロジェクトとして運営すれば、さらなるコミュニケーション活性化が期待できます。
コミュニケーションツールの導入
適切なコミュニケーションツールの導入は組織のコミュニケーション活性化に不可欠です。特に、異なる場所で働く社員同士がスムーズに情報共有や意見交換ができるよう、慎重にツールを選定しましょう。
一般的にコミュニケーションツールは、ビジネスチャットツールやWeb会議システム、ナレッジ共有ツールなどが挙げられます。
ビジネスチャットツールは、メールよりも素早くカジュアルなコミュニケーションを可能にします。Web会議システムは、離れた場所にいても顔を見ながら会話ができ、非言語コミュニケーションも含めた豊かな対話が可能です。
コミュニケーションツールは、多様化する働き方に対応するための軸となる手段といえるでしょう。
シャッフルランチ
シャッフルランチは、普段接点の少ない社員同士が食事を共にする制度です。3〜5人程度のグループを会社がランダムに編成し、月に1〜2回程度の頻度で実施されます。会社が食事代を負担するため、社員にとっては気軽に参加できるイベントです。
シャッフルランチの最大のメリットは、部署や役職の壁を超えた交流が生まれる点です。普段は話す機会のない人と食事をすれば、新たな視点や情報を得られるでしょう。
また、シャッフルランチは単なる親睦の場ではなく、イノベーションの種を生み出す場にもなり得ます。異なる専門性を持つ社員同士が気軽に意見交換することで、思わぬアイデアが生まれるのです。
部署や勤続年数などを考慮したグループ編成を心がけるなどして、参加者の多様性を確保して実施しましょう。
フリーアドレス制度
フリーアドレス制度は、固定席を廃止し社員が毎日自由に席を選べるようにする制度です。
フリーアドレス制度のメリットは、社員間の交流が増える点にあります。毎日異なる人の隣に座るため、接点の少ない部署の人とも自然に会話する機会が生まれます。
また、社員の柔軟性と創造性の向上もフリーアドレス制度のメリットです。環境の変化が刺激となるため、新しいアイデアが生まれることもあるようです。
フリーアドレス制度を成功させるためには、ITインフラの整備が不可欠です。ノートPCやクラウドストレージの導入など、どの席でも快適に仕事ができる環境を整えましょう。社員の理解と協力が必要です。メリットを明確に説明し、段階的に導入しましょう。
関連記事:インターナルブランディングとは?成功に導くためのステップや注意点について紹介
組織コミュニケーションの成功例
複数の事業所を持つA社は、組織コミュニケーションに課題を抱えていました。営業部門の最新情報が製造部門に伝わらず、顧客ニーズに合った製品開発が遅れがちだったのです。そこで、全社的な情報共有ツールを導入し、各部署の日々の活動や成果を共有する仕組みを作りました。
情報共有ツール導入後は、営業部門の日報に製造部門がすぐにコメントを返せるようになり、頻繁な情報共有が行われています。また、経営陣も定期的にメッセージを発信し、会社の方向性を全社員と共有するようにしました。さらに、離れた事業所の社員同士でも、互いの仕事内容や課題を理解し合えるようになり、会社全体に一体感が生まれました。
この成功例は、ツールの導入と活用する文化づくりの両輪が重要であると示しています。
組織コミュニケーションの失敗例
同じように情報共有ツールを導入しても、組織コミュニケーションの活性化につながらなかった例もあります。
社内のコミュニケーション活性化を目指して社内SNSを導入したB社では、部署間の垣根を越えた情報共有や、新しいアイデアの創出が行われるだろうと期待が高まっていました。
しかし、導入から半年が経過しても、期待していた効果は現れません。実際にSNSを活発に利用しているのは、全社員の約2割程度で、そのほとんどが若手社員だったのです。中堅社員や管理職の多くはSNSをほとんど利用せず、「仕事の邪魔になる」「使い方がわからない」といった声も聞かれました。
B社の事例は、ツールの導入だけでは解決につながらないことを示しています。
まとめ
企業の成長や社員のモチベーション向上のためには、組織コミュニケーションは不可欠です。本記事では組織コミュニケーションの重要性や、具体策について解説しました。自社には問題ないと考え、組織コミュニケーションを放置していると、ミスやトラブルの増加や離職率の上昇、顧客の信用喪失など多くの問題につながりかねません。
現状に満足せず、1on1ミーティングや社内報、コミュニケーションツールの導入、シャッフルランチ、フリーアドレス制度といった具体策を取り入れ改善を継続しましょう。最後に紹介した成功例と失敗例を参考に、自社の組織コミュニケーションを活性化させ、業務効率や生産性の向上を手に入れてください。